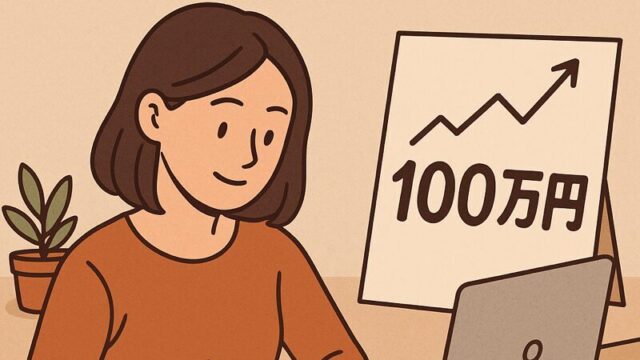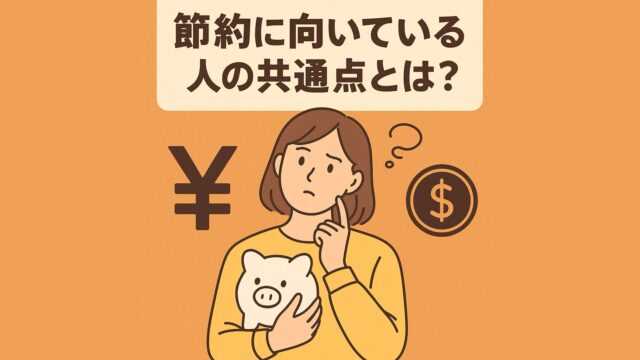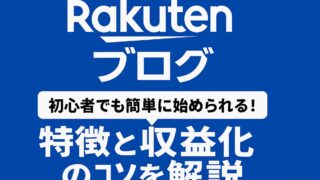なぜ節約がうまくいかないのか?
節約がうまくいかない人の多くは、すべての出費を一律に減らそうとしてしまう傾向があります。
しかし、それではストレスがたまりやすく、長続きしないのが実情です。
節約を成功させるために最も大切なのは、出費に優先順位をつけることが大切です。
先ずはあなたの1ヶ月の支出を振り返り、出費をカテゴリごとに分類してみましょう。
そのうえで、自分にとって「大切な出費」と「そうでない出費」を分けていきます。
- 優先順位の高い出費(あなたにとって大切な支出)→ 節約の対象外
- 優先順位の低い出費 → 思い切って削減
特に、優先順位が低く、かつ記憶に残らないような出費は、節約の第一候補です。
このようにメリハリをつけることで、節約が苦手な人でも無理なく始められますし、
ストレスを感じることなく、持続可能な節約習慣を築くことができるでしょう。
この記事では具体的な手順を紹介していきます。
記憶に残らない出費とは?
「記憶に残らない出費」とは、使ったことすら思い出せないような支出のことです。
たとえば、あなたはこの1週間で食べた昼食をすべて思い出せますか?
昨日の昼ごはんは覚えていても、おととい、3日前のランチはもう曖昧かもしれません。
あるいは、コンビニで買ったエナジードリンクや缶コーヒーなど、仕事の合間に「なんとなく」買ったもの。これらも、おそらく記憶にないのではないでしょうか。
一方で、大切な人との食事や、旅行先での食事のような「記憶に残る出費」は、何年経っても心に残るものです。
優先順位の低い出費=記憶に残らない出費、とは限らない
ここでひとつ確認しておきたいのは、
「記憶に残らない出費」=「優先順位が低い出費」とは必ずしも一致しないということです。
たとえば、健康保険料や通勤定期券などは、使った記憶には残りにくいかもしれません。
しかし、これらは生活を維持したり、もしもの時には欠かせない、優先度の高い支出です。
逆に、優先順位が低く、かつ記憶にも残らないような出費も日常のなかに数多く潜んでいます。
たとえば:
- 仕事の合間に何となく買っている缶コーヒー
- 眠気覚ましに寄ったコンビニでのスナック菓子
- 使うか分からないままなんとなくカゴに入れた日用品
- 週に何度も頼んでしまう同じようなランチのデリバリー
これらはほとんどの場合、「何にいくら使ったのか」すら覚えていないことが多く、生活に与える影響も大きくありません。
だからこそ本記事では、
「記憶に残らず、かつ生活や価値観において優先順位が低い出費」
この重なり合うゾーンを、節約の第一歩として見直すことをよく提案しています。
記憶に残らない x 優先順位の低い出費を “最安で済ませる”ことで得られる効果
では、あなたにとって優先順位が低い出費を見直した場合、どれくらいの節約効果が得られるのでしょうか?
仮に、毎日仕事おわりに缶ビール2本、仕事の合間にカフェにに立ち寄っているとしましょう。
▷ ビール2本 → 1本に
- 1本250円の缶ビールを毎晩2本 → 500円
- それを1本に減らせば、250円の節約
▷ カフェのテイクアウトコーヒー → 自宅ドリップコーヒー
- カフェのラテ:1杯500円前後
- 自宅ドリップ:1杯約30円程度(豆代+フィルター代)
- 差額は約470円の節約
この2つを組み合わせれば、1日あたり500円の節約は簡単です。
私自身、日中のコーヒーは職場の共用のドリップコーヒーを使っています。
月額1,000円を支払えば、飲み放題制度のような形で利用でき、私は1日に2〜3杯飲んでいます。
仮に1ヶ月20日出勤として計算すると、40〜60杯/月。
1杯あたりに換算すると、約17〜25円という低コストです。
この量を仮にコンビニコーヒーにしていたらと思うと、月に1万円以上の出費になることは確実です。
このように、「記憶に残らない出費」を最安で済ませる工夫を取り入れるだけで、
生活の満足度をほとんど下げずに、しっかりと節約効果を得ることができます。
節約とストレスのバランスのとり方
節約を継続するうえで、ストレスとのバランスをどう取るかはとても重要です。
過度な節約は、ダイエットの「リバウンド」と同じで、反動で出費が一気に増えてしまうリスクがあります。
我慢に我慢を重ねて節約していたのに、ある日どかっと買い物してしまっては、本末転倒です。
だからこそ、無理のない節約ルールを自分で作ることが大切です。
私は節約を「ゲーム感覚」で楽しむようにしています。
たとえば、
- 今日は何円浮いたか?
- その浮いた分をどう使うか?
- この500円が将来どう増えるか?
といった視点で日々の節約を「スコア化」してみると、少し前向きに取り組めるようになります。
ただし、ゲーム感覚でやっていても、楽しくない節約はやはりストレスになります。
たとえば、自分にとって優先度の高い出費を削るような節約は、ゲームとして捉えていても我慢の連続で、長続きしませんでした。
だからこそ大切なのは、“何を節約し、何を守るか”の優先順位をしっかりと決めておくこと。
自分にとって価値の低い出費だけを削ることが、ストレスなく続けられる節約のコツです。
浮いたお金はどう活かす?(副業・投資へ)
こうしてストレスなく節約できたお金は、ぜひ「未来の自分」のために活かしてみてください。
私の場合、その一部を投資に回すことにしています。
もちろん、投資先は株式だけに限る必要はありません。
自己投資、副業資金、学習教材など、使い方は人それぞれです。
ですが私は、株式投資をおすすめします。理由はシンプルで、時間をかければかけるほど“複利の力”が効いてくるからです。
▷ 毎日500円の節約を投資に回した場合
たとえば、1日500円を節約して、それを年間240日(平日ベース)投資に回すとします。
年間の積立額は 500円 × 240日 = 12万円 になります。
これを、年利5%で10年間運用すると、最終的な資産額は:
💡 約1,540,000円(154万円)になります。(元本120万円+運用益約34万円)
たった1日500円の節約でも、10年で150万円を超える資産になる可能性があるのです。
▷ 10年後、節約の意味は変わってくる
もちろん、10年後には1日500円の価値なんて気にしない生活になっているかもしれません。
そのときは、優先順位の高い出費に+500円を使ってより記憶に残る出費を贅沢に楽しめばいいのです。
でも、今の小さな習慣が、後の大きな自由をつくるのは間違いありません。
おわりに|「選んでお金を使う」生き方へ
節約がなかなか始められない人に共通しているのは、すべての出費を平等に「欲しいもの」として捉えてしまっていることかもしれません。
けれど実際は、すべてを手に入れることはできないからこそ、優先順位をつけることが大切です。
まずは、自分にとって本当に価値のある出費を見極めてみましょう。
そのうえで、優先順位の高い出費は削らずに守り、逆に「記憶に残らない」「生活にほとんど影響のない」出費から見直すことをおすすめします。
お金の使い方は「量」よりも「選び方」。
節約とは、「我慢」ではなく、「選択」なのです。
https://fukugrow.jp/?cat=22