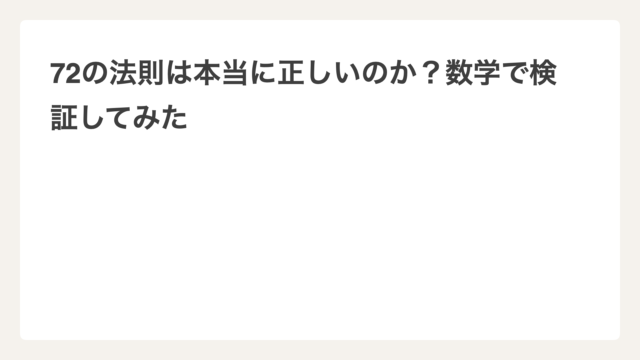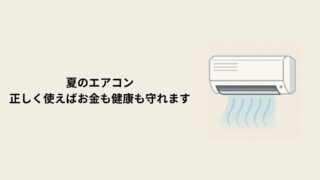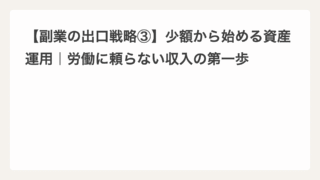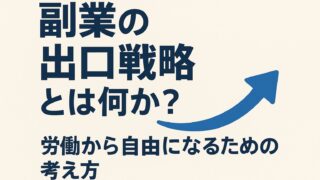一人暮らしって、自由ですよね。
好きな時間に寝て、好きなものを食べて、誰にも気を遣わない。最高。
…だけど、気づいたらお金が消えてる。
「え、今月もう残高これだけ? 何に使ったっけ?」なんて日も、正直なところ何度もありました。
私も大学進学をきっかけに一人暮らしを始め、最初は親からの仕送りとバイト代でやりくりしていました。
社会人になってからは収入こそ増えましたが、「自分で全て払う生活」って、思ったよりずっとお金がかかる。
しかも、無理な節約は全然続かないんです…。
だから私は、“ムリなく続けられる節約”を少しずつ見つけていきました。
がんばりすぎず、それでいて月に2〜3万円はちゃんと浮いてくるような節約術。
10年近く一人暮らしをしてきた中で、実際に「これは効果があった」と感じた習慣を、本記事ではまとめてご紹介します。
節約って、「我慢大会」じゃありません。
ちょっとした工夫で、ちゃんと生活の質も保ちつつ、ムリせずお金を残すことはできるんです。
「節約したいけど、つらいのはイヤ」
「節約って、結局なにから始めればいいの?」
そんなあなたに、等身大の体験をもとにしたヒントを届けられたら嬉しいです。
節約の考え方|ムリしない=持続可能性
「節約=我慢」と思っていませんか?
正直、私もそうでした。
毎日お弁当、冷房もなるべくつけず、外食なんてもってのほか。
そんな生活を頑張っていた時期もあります。
でも、数週間は続いても、ある日ぷつんと糸が切れたようにやめてしまうんですよね。
結局コンビニで爆買いして、ストレスで逆に出費が増える…なんて本末転倒なことも。
それで気づいたんです。
節約って、「我慢の積み重ね」じゃなくて、「ムリなく続けられる仕組みづくり」なんだなって。
ポイントは「コスパ」と「タイパ」
最近よく聞く「コスパ(コストパフォーマンス)」に加えて、私は「タイパ(タイムパフォーマンス)」も重視するようになりました。
たとえば、自炊が節約になるとはいえ、毎日1から作って片付けていたら、時間がいくらあっても足りません。
そんな時は、冷凍食品や作り置きを活用して、自分の時間を節約することも立派な節約。
お金を節約したいのに、心や時間をすり減らしてしまったら意味がありません。
節約は、自分を苦しめるものじゃないんですよね。
節約は「習慣」になったら勝ち
節約って、続けられないと意味がありません。
でも逆に言えば、「習慣化」さえできれば、意識しなくても勝手にお金が貯まっていく状態になります。
- 毎朝コンビニに寄らなくなった
- サブスクを減らしたことで、見たい番組にちゃんと集中できるようになった
- 冷凍ごはんが常備されているから、外食に頼らなくて済む
こういうちょっとしたことが積み重なるだけで、月に数千円、年間では数万円の差が出てきます。
自然と節約してる状態が“理想形”
理想は、「あれ、いつの間にかお金が残ってる」という感覚です。
そのためには、ムリなく・ラクに・自分の性格に合った節約方法を見つけることが大事。
このあとの章では、実際に私が一人暮らしでムリせず続けられた具体的な節約術を紹介していきます。
固定費から食費、光熱費まで、「効果が出たもの」だけを厳選してお伝えしますので、あなたに合いそうな方法がきっと見つかるはずです。
「がんばらない節約」で、少しずつ生活を軽やかにしていきましょう。
固定費の節約術(まずここから!)
節約をはじめるなら、まず固定費を見直すことが一番効果的です。
なぜなら、一度固定費を下げれば「放っておいても」その節約効果を得られるからです。
まさに、「頑張らない節約」です。
家賃の見直し|まずは「住まいの固定費」に注目
大学生のときは、正直なところ家賃なんてあまり意識していませんでした。
親が契約してくれていたこともあり、ありがたいことにそのままの環境で生活できていたからです。
でも、社会人になってからは話が別。
自分の収入でやりくりしてみると、「家賃って想像以上に重たい固定費なんだな」と痛感しました。
住まいにかかるお金は、一人暮らしにおいて最も大きな出費のひとつ。
だからこそ、「今の家賃、本当に妥当?」と一度立ち止まって見直してみる価値があります。
私自身は、固定費を抑えるために社員寮を活用したことがあります。
家賃も光熱費もかなり抑えられ、家具家電付きで初期費用がほとんどかからないのが大きな魅力でした。
もちろん、寮には独特のルールや制限もあり、万人に合うとは限りません。
でも、もし今あなたが新卒や転職のタイミングで企業選びをしているなら、「住宅補助の有無」や「寮の制度」は固定費に直結する要素なので、一つのチェックポイントとして見ておくと良いかもしれません。
「引っ越すほどじゃないけど、家賃は気になる…」という方は、
- 立地を少し妥協する
- 築年数の古い物件を視野に入れる
- 家賃交渉をしてみる
などの方法でも家賃を抑えられるケースがあります。
住まいは生活の土台ですが、必要以上にお金をかけすぎない工夫も、節約生活ではとても重要です。

サブスクの見直し|“惰性の契約”ありませんか?
次に見直したのが、サブスクリプション系の支出です。
Netflix、Spotify、YouTube Premium、雑誌系アプリ、ジム…いつのまにか増えていませんか?
私のルールはとてもシンプル。
- ○ よく使ってる → 継続OK
- × あまり使ってない → 即解約
- △ なくても困らない →「必要なときに単発で買う」に切り替える
実際、「なくても平気だったな」と思ったサブスクは多かったです。
逆に、YouTube Premiumのように「生活の満足度が上がる」ものは継続しています。
節約=全部やめる、じゃなくて、“価値を感じるものだけに絞る”ことが大事なんですよね。
電気・ガスのセット割|見直すだけで数千円の差
電気とガスを別々の会社で契約している方、意外と多いと思います。
私も最初はそうでした。でも、ある日ふと気づいたんです。「これ、セットにしたら安くなるのでは?」と。
調べてみると、電気+ガスのセット契約で月に500〜1,000円ほど安くなるプランが多数存在。
しかも、契約変更もオンラインで10分もあれば完了します。
電力自由化・ガス自由化で選べる会社が増えた今こそ、「なんとなく契約しっぱなし」を見直すチャンスです。
保険の見直し|“必要なものだけ”に絞る
最後に見直したのが保険です。
学生時代から入っていた医療保険や、自動車保険の特約など、なんとなく惰性で払っている保険料ってありませんか?
もちろん、保険は「いざという時の安心」ではあります。
ですが、貯金や生活防衛資金がしっかりある人にとっては、不要な保険も少なくありません。
私が実際に見直したときのポイントは以下の通りです:
- 民間医療保険:会社の健康保険と貯金でカバーできる範囲はカット
- 火災・地震保険:最低限は残し、オプション特約は削減
- 自動車保険:運転頻度とリスクに見合った内容に調整
もちろん、「本当に必要な保険」は絶対にやめてはいけません。
でも、必要な保障と“なんとなくの安心料”を分けて考えることで、毎月の支出はかなりスリムになります。
おすすめ:格安SIMに乗り換えるだけで年間1万円以上の差も
これは通信費にも関わりますが、スマホ代は“見直し効果の大きい固定費”の代表格です。
私は楽天モバイルに乗り換えて、データ通信無制限で月3,000円以下になりました。
通信制限なしでテザリングも可能、しかも契約の縛りなし。
今まで7,000〜8,000円払っていたことを思うと、もはや戻れません。
固定費の節約は、「面倒そう」に見えて、一度やればずっと効果が続く“最強の節約術”です。
まずは、あなたの固定費リストを書き出して、「これ、今も価値ある?」と問いかけてみてください。
次の章では、食費の節約術をご紹介します。ムリしない、でもちゃんと満足できる食生活の工夫も、実体験をもとにお話ししていきますね。
食費の節約術(でもちゃんと食べたい)
食費って、節約しようとするとすぐに効果が出やすい反面、ムリをすると一番つらいところでもあります。
食べるって、心の健康にも直結してますからね。
私も以前、1日300円生活にチャレンジしたことがあるんですが、3日で挫折しました…。
「節約=空腹」と感じた時点で、それはもう続かないんだなと痛感。
だからこそ私は、「ちゃんと食べたい。でもムリせず節約もしたい」という、ちょっとわがままなスタンスで食費と向き合うようになりました。
冷凍庫が大きい冷蔵庫は、最強の節約家電
一人暮らしの自炊が難しい最大の理由、それは「1人分ってコスパが悪い」から。
でも、数日分まとめて作って冷凍しておけば、実質的には“自分のために数人分のごはんを作っている”ことになります。
私が最初にやった節約は、大きめの冷凍庫付き冷蔵庫に買い替えたことでした。
これが思いのほか大正解。
冷凍ストックがあるだけで、「今日は疲れたし外食しようかな…」という誘惑に勝てる回数がぐっと増えました。
- ごはんはまとめて炊いてラップ冷凍
- おかずは3〜4品を週末に作り置き&冷凍
- 野菜も冷凍野菜を活用してロスなし
このスタイルにしてから、食費が1ヶ月あたり6,000〜8,000円は浮くようになりました。
自炊のハードルを下げる工夫
「料理はちょっと苦手…」「毎日はムリ」という方も大丈夫。
自炊って、“毎日頑張るもの”じゃなくていいんです。
たとえば私がやっていたのは:
- レトルトカレーに冷凍ブロッコリーを足すだけ
- インスタント味噌汁+玄米ごはん+納豆
- オーケー(関東圏の格安スーパー)で買ったお惣菜を小分け冷凍
つまり、「ゼロから全部作らなくていい」という気持ちが大事。
「一部だけ作る」とか、「ちょっと足す」くらいでも、十分“自炊のうち”です。
格安スーパーは味方。オーケーは神コスパ
節約を意識してから、スーパー選びにもこだわるようになりました。
特に関東圏の方なら、「オーケー」は本当におすすめ。
商品が安いだけでなく、品質もしっかりしていて、「安かろう悪かろう」じゃないのがうれしいところ。
もちろん他の地域でも、「業務スーパー」「ロピア」「トライアル」など、コスパが良いお店は探せば意外と身近にあります。
外食・コンビニは「ルール化」でゆるく管理
全部自炊にしようとするとストレスが爆発するので、私は“週に2回まで外食OK”というマイルールを設定しています。
それに加えて、「1回あたりの外食予算は1,000円以内」という軽い縛りも。
このくらいのゆるさなら、
「今日は疲れたから外食したい!」
「友達とカフェに行きたい!」
という気持ちも満たしながら、しっかり予算内に収まるようになります。
逆に、予算を決めずに“なんとなく”使っていると、気づけばコンビニだけで月1万円近く使っていた…なんてことも。
食費は“ムリなく満足”がいちばんコスパがいい
節約において、食費は我慢と表裏一体。
だからこそ、無理をしない工夫=続けられる工夫がとても大切です。
- まとめて作って冷凍する
- 半自炊スタイルを取り入れる
- スーパーを見直す
- 外食は「回数×金額」でルール化する
これだけで、ストレスなく、でも着実に食費を抑えることができます。
次の章では、日用品・雑費の節約術をご紹介します。
こちらも「買いすぎ」「使いすぎ」に気づけるだけで、大きな効果が出るジャンルですのでお楽しみに!
日用品・雑費の節約術
正直なところ、日用品やちょっとした雑費って「なんとなく」で買ってしまいがちじゃないですか?
私は以前、コンビニでティッシュや電池を買っていたこともありました。でも、よく考えると“いつも買っているもの”こそ節約の余地があるんですよね。
この章では、私が実際に取り入れてよかった「ムリせず・地味だけど効果のある」日用品&雑費の節約術を紹介します。
ドラッグストアのアプリクーポンを味方にする
まず試してほしいのが、ドラッグストア公式アプリのクーポン活用です。
スギ薬局、ツルハ、ウエルシア、ココカラファインなど、今はどこのお店にも公式アプリがあります。
使い方はとてもシンプルで、レジで提示するだけ。
- お誕生日月の特別割引
- ポイント倍デーのお知らせ
- 「ティッシュ10%オフ」「洗剤20円引き」などの限定クーポン
これだけで、日用品が “いつもより確実に安く買える” ようになります。
私はスギ薬局アプリの「15%オフクーポン」に何度助けられたかわかりません…。
普段の買い物にアプリを組み合わせるだけで、数百円浮くのは地味に大きいです。
ポイ活アプリで「いつもの買い物」をもっとお得に
次におすすめなのが、「ポイ活アプリ」を通じた買い物。
私はハピタスと楽天リーベイツを使っています。
やることはたった一つ。楽天市場やYahoo!ショッピングなどの通販サイトを、アプリ経由で開くだけ。
それだけで、
- 通常ポイントに加えて1〜5%分のポイントがプラス
- 楽天なら「買いまわり」や「マラソン」と組み合わせると最大10倍以上の還元も
たとえば、トイレットペーパーや洗剤などを楽天市場でまとめ買いする前に、ハピタスを経由するだけでポイント二重取りができるんです。
さらに、楽天カード払いにすれば三重取りも。
一度登録して使い方に慣れてしまえば、ほぼノーリスクで得する習慣になります。
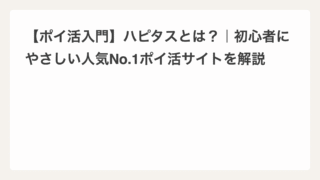

買いすぎ・ストックしすぎを防ぐ「チェック習慣」
節約のつもりで日用品をまとめ買いしたのに、「あ、これ家にまだ3つあった…」なんて経験ありませんか?
私も以前、トイレットペーパーやラップをダブって買ってしまうことがよくありました。
これを防ぐためにやっているのが、
- 家にあるストックをスマホメモに書いておく
- 買い物前に軽くチェックする習慣をつける
というシンプルなルール。
面倒に見えるかもしれませんが、たったこれだけで「ムダな出費」と「収納スペースの圧迫」を防げるようになります。
楽天お買い物マラソンでまとめ買い
ネットでまとめ買いするときは、楽天お買い物マラソンのタイミングを狙うのも効果的です。
- 複数店舗での購入でポイント倍率がUP
- ハピタス経由でさらにポイント追加
- 日用品や消耗品も対象商品が多いので、実用的かつお得
私も、洗剤・スポンジ・歯ブラシ・シャンプー・カミソリ…など、半年に一度くらいのタイミングでまとめ買いしています。
一度に数千円は浮くので、これだけでちょっとした“副収入感”が得られます。
このジャンルで一番大事なのは、節約を「クセづけ」できるかどうかです。
- アプリを入れておく
- クーポンを確認する癖をつける
- ストックを把握する
- 買う前に一度ネットをチェックする
これを“無意識でやれるようになる”と、月に1,000〜2,000円くらいは自然と浮いてきます。
しかも、「我慢ゼロ」で。
次の章では、光熱費・通信費の節約術をご紹介します。こちらも一度見直すだけで効果が長く続く“コスパ最強ゾーン”です。
光熱費・通信費の節約術
固定費の次に見直したいのが、毎月じわじわと出ていく「光熱費」と「通信費」。
一見「変動費っぽい」ようでいて、見直せば意外と長期的な効果が出るジャンルです。
どれも一人暮らしに欠かせないインフラだからこそ、「ムリしないけど無駄にしない」バランス感が大切になります。
エアコンは「つけっぱなしvsこまめに消す」論争、どっちが正解?
これは本当に悩ましい問題ですよね。
私も最初の夏は、エアコン代が怖くて汗だくになりながら我慢していました…。でもそれって体に悪いし、結局ストレスでアイスを爆買いして出費が増える、なんてことも。
で、調べたんです。
エアコンは「つけっぱなし」と「こまめに消す」どちらが節電になる?【XPRICE】
結論から言うと、「短時間の外出ならつけっぱなしの方がむしろ安い」です。
なので、私は夏も冬も「外出が1時間以内ならそのまま、長時間ならオフ」という運用に切り替えました。
さらに、扇風機やサーキュレーターを併用することで、設定温度を控えめにしても快適に過ごせるように。
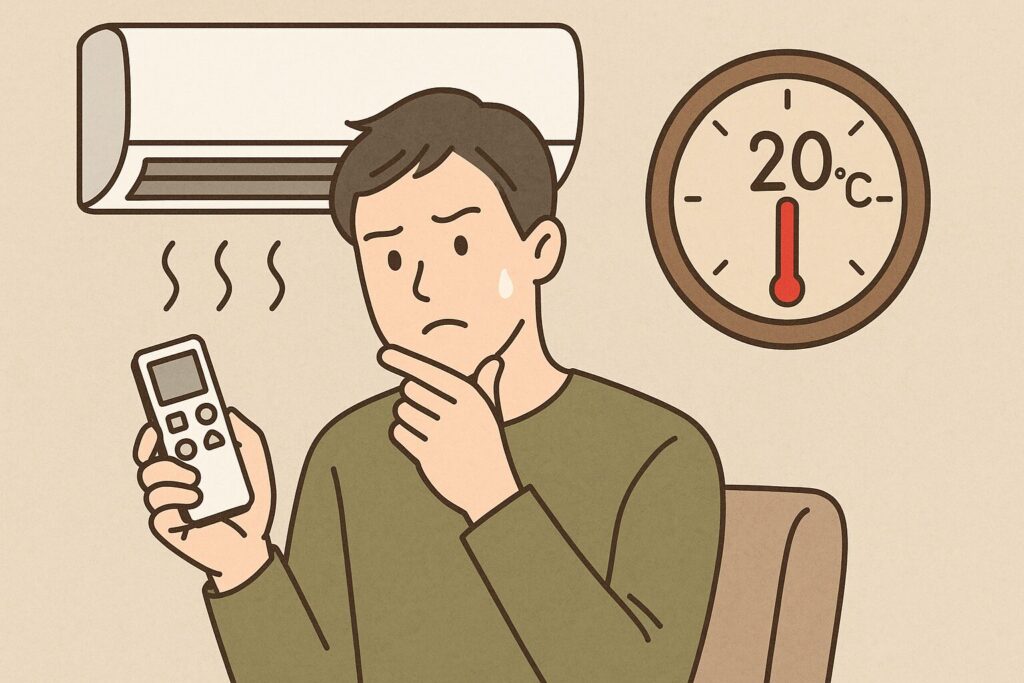
電気代を節約する「5つの小技」
- 待機電力カット:使ってない家電のコンセントは抜く or 節電タップ活用
- 冷蔵庫の温度設定を見直す(冬は「弱」でも十分)
- 洗濯はまとめ洗い+夜間の安い時間帯に回す
- LED照明への切り替え
- 電力会社を比較して乗り換え(地域電力から新電力へ)
正直、1つずつは小さな効果ですが、全部合わせると月に1,000円以上変わることもあります。
Wi-Fiって本当に必要?→ テザリングという選択肢も
「一人暮らしのWi-Fi契約、本当にいる?」
これは何度も自問しました。
答えは、「スマホが無制限なら、必ずしもWi-Fiはいらない」です。
私は楽天モバイルのテザリング機能を使って、
- ノートPCでの作業
- ネット動画の視聴
- Zoom会議 など
すべてカバーできています。もちろん住環境や仕事の性質によってはWi-Fiの方が安定して使える場面もありますが、「とりあえず契約してる」状態なら見直す価値ありです。
光熱費・通信費を節約するための行動チェックリスト
| 項目 | やること | 節約効果の目安 |
|---|---|---|
| エアコン | 外出1時間以内はつけっぱなし+サーキュレーター併用 | 月500〜700円 |
| 待機電力 | コンセント抜く・節電タップ使用 | 月数百円 |
| スマホ料金 | 格安SIM(楽天・povo・IIJmio等)に変更 | 年間5〜6万円 |
| Wi-Fi契約 | テザリングで代用可能か検討 | 年間3〜4万円 |
光熱費も通信費も、「契約しっぱなし」や「昔からの習慣」のままだと、無駄が生まれがちです。
でも、一度見直してしまえば、その効果は翌月から確実に数字で返ってくる。
次の章では、節約を“続ける”ためのコツとメンタル管理術をご紹介します。
節約の「続け方」とメンタル管理
節約って、はじめの一歩は意外と簡単だったりします。
問題は、それをどう「続ける」かなんですよね。
気合いで頑張っても、三日坊主で終わってしまった経験…私にも何度もあります。
でも、うまく“仕組み化”したり“気持ちを整える工夫”をすることで、節約は思ったよりラクに続けられるようになりました。
まずは「見える化」から|家計簿アプリ or 予算表
節約を始めたばかりのころ、私が最初に挫折した理由は、「何にいくら使っているのか分からなかったから」でした。
その解決策が、「見える化」です。
おすすめは家計簿アプリ。私が使っているのは「マネーフォワード ME」や「Zaim」など、銀行口座やクレカと連携できるもの。
- 自動で支出を分類してくれる
- グラフで月ごとの傾向が見える
- 「今月あといくら使えるか」がひと目で分かる
アプリが合わない人は、シンプルにExcelやノートで“手書きの予算表”を作るのもアリ(個人的にはこれは三日坊主だったので、すぐにアプリに移行しました)。
ポイントは、「ざっくりでいいから、使った金額を自分の目で確認すること」。これだけで、無駄な支出がぐっと減ります。
ご褒美予算をつくろう|反動を防ぐために
「節約生活が続かない…」という人に共通しているのは、“我慢しすぎている”こと。
だからこそ、私は「ご褒美予算」をちゃんと作っています。
たとえば…
- 月に1回のちょっと贅沢なランチ:1,500円までOK
- お気に入りのスイーツ:週1回までOK
- スパやマッサージ:3ヶ月に1回ご褒美としてOK
こういう“心が喜ぶ出費”をあらかじめ予算に組み込んでおくと、
「節約=苦しいもの」ではなくなります。
「完璧を目指さない」が一番大事
最後に伝えたいのが、「完璧主義にならないこと」。
1ヶ月で2万円節約できた月もあれば、3,000円しか残らなかった月もあります。
でも、それでいいんです。
むしろ、「使いすぎちゃった月」もデータとして残しておけば、
「次はここを気をつけよう」と前向きに振り返る材料になります。
私自身、「節約に失敗した月こそ、学びが多いな」と感じています。
節約は、マラソンのようなもの。
無理して走っても途中でバテてしまうなら、ちょっと歩きながらでもいいから、ゴールに向かって続ける方が大事。
- 家計簿やアプリで「今の自分のお金の流れ」を見える化
- 自分を責めないためのご褒美予算をあらかじめ用意
- 完璧じゃなくても、続けられることが何よりの正解
この3つを意識するだけで、節約は我慢の連続ではなく、自分の暮らしを整えていく心地よいプロセスに変わっていきます。
次の章では、「実際にやってみて失敗だった節約」=やめてよかった節約術についてご紹介します。
私が実際にやめた節約術(逆効果だった…)
ここまで読んで「節約って意外と楽しくできるかも」と感じてくれていたら嬉しいのですが……
実は私にも、「これは続かなかった」「逆に損をした」節約法があります。
節約は、自分に合ったやり方を見つけるのが何より大事。
だからこそ、やめてよかった節約法=自分に合わなかった方法をあえてシェアしておきます。
無理な自炊生活|「節約のために毎日料理」は続かない
一時期、気合いを入れて「毎日3食自炊生活」を目指したことがありました。
冷凍食品や外食をゼロにして、完全に手作りオンリー。もちろん、食費は一時的にかなり抑えられました。
でもその代わりに…
- 夜遅く帰宅してからの料理に疲れ果てる
- 洗い物がたまってキッチンを見るだけでストレス
- 食べきれずに食材を無駄にしてしまう日も…
結果として、ストレスでコンビニ爆買い→リバウンド支出という本末転倒なサイクルに。
節約で大事なのは「継続できること」。
それ以来、私は“半自炊”スタイルに切り替えました。
- 朝は納豆+冷凍ごはん+インスタント味噌汁
- 夜は作り置き+冷凍食品を組み合わせて15分以内で完成
これだけでも食費はしっかり抑えられますし、ストレスも最小限。
自炊は「量より質」「毎日より続け方」で考えるのがコツだと思います。
「安かろう悪かろう」に何度泣いたか…モノの買い替え地獄
もう一つ後悔しているのが、とにかく安いものだけを選ぶクセです。
当時の私は、「どうせ1人暮らし用だし」と思って、
100均のキッチンツールや、ノーブランドの格安家電をとにかく揃えていました。
でも結果は…
- おたまやフライ返しはすぐに反って使いにくくなる
- 安いドライヤーは風量が弱くて毎日イライラ
- 激安掃除機は吸引力が弱すぎて結局ホコリが残る
そして、結局1年も経たないうちに買い替え。
初期投資をケチったばかりに、「2回買って、最初より高くつく」という典型的なパターンにハマりました。
それからは、「毎日使うものには、ある程度の質と耐久性を求めるべき」と考えるように。
今では、多少高くても“いいモノを長く使う”ほうが結果的にコスパが良くなると感じています。
無理な節約は「損」になることもある
- 自炊は“やりすぎ”ない
- 安さだけでモノを選ばない
この2つは、私の節約経験の中でも特に大きな教訓です。
節約って、なんとなく「全部を削ること」と思われがちですが、本当に大事なのは「削るべきもの」と「残すべきもの」の線引きです。
そしてその線は、人によって違います。
自分の暮らしと心のバランスを見ながら、無理なく・楽しく・持続可能な節約スタイルを見つけていきましょう。
絶対におすすめしない節約|医療費を削る=将来の健康リスクを高めるだけ
ここまで色々な節約の話をしてきました。ただ、その中で唯一削ってはいけない出費があります。
それは医療費です。
これだけは、絶対に削ってはいけない出費です。
理由はシンプル。いまの小さな節約が、将来の大きな負担やリスクにつながるから。
歯科検診をケチると、将来の“高額出費”に直結する
「歯医者って面倒だし、痛くなったら行けばいいでしょ」――
でも実は、虫歯や歯周病って“沈黙の病気”。
痛みが出たときには、すでに症状がかなり進行していることも少なくありません。
虫歯に関するエビデンス
- 虫歯は痛いだけではありません。
- 歯周病は糖尿病や心疾患のリスクを高めると複数の研究で指摘されており、結果的に医療費にも影響
つまり、年1〜2回の定期検診を惜しんだ結果、高い治療費+通院時間+健康面でのデメリットを負うこともあるのです。
参考文献:歯周病と全身の病気とのつながり 【日本歯科医師会HP】
健康診断やがん検診を後回しにしてはいけない理由
もう一つ見逃せないのが、「健康診断」や「がん検診」の重要性。
たとえば、大腸がんを例に取ってみましょう。
早期発見であれば体への負担が少なく、日帰りや短期入院で済むケースも少なくありません。一方で、発見が遅れ進行がんとなった場合、手術だけでなく抗がん剤治療、長期入院、さらには再発予防のための通院や生活習慣の見直しが必要になるなど、心身への負担は一気に跳ね上がります。
参考文献:早期大腸がんの低侵襲な内視鏡治療 【国立がん研究センター中央病院HPより】
そして何より、がんの進行度が高くなるほど、生活そのものが制限される可能性が高まります。仕事を一時的に休まなければならなくなったり、家事や趣味に割ける時間が減ったり、人によっては「自分らしい生活」が大きく損なわれることもあるのです。
それに加えて、再発への不安や、通院・治療にともなうスケジュール管理の煩雑さ、周囲への気遣いなど、精神的なストレスも決して小さくありません。
「ちょっと面倒」「お金がもったいない」――そんな理由で受診を後回しにすることで、気づかぬうちに将来の大きな負担を背負い込んでしまうこともあります。
もちろん、すべての病気や悪性腫瘍が予防できるわけではありません。中には、どれだけ注意していても防ぎきれないものもあります。
それでも、大腸がんや子宮頸がん、胃がんなど、一部のがんは早期に見つければ比較的軽い治療で済むケースが多く、予防や早期発見が効果的とされている分野も確かに存在します。
だからこそ、健康診断やがん検診は「節約の対象」ではなく、“リスクを減らせるものにはきちんと備える”という視点で捉えてほしいのです。
これは単なる出費ではなく、未来の自分と大切な人たちの時間・健康・安心を守るための「賢い使い方」=自己投資だと、私は考えています。
「将来の医療費を抑える」という意味で、定期的な受診を
節約の本質は、「お金を使わないこと」ではありません。
「使うべきところには、使う」ことも立派な節約です。
とくに医療費は、
- 早期に使えば少額で済む
- 放置すれば10倍、100倍の出費になる可能性がある
- そして何より、自分の人生の質(QOL)を左右する
という特殊な性質を持っています。
次の章では、これまでの内容を振り返りながら、無理なく続けられる「一人暮らし節約術」のまとめをお届けします。

まとめ|あなたの暮らしに合った“ゆる節約”を
「節約=つらい」「がまんの連続」
そんなイメージを持っていた私ですが、今回ご紹介してきたように、実際には“ゆるくてもしっかり効果がある節約”はたくさんあります。
頑張って節約しても、疲れてやめてしまったら意味がありません。
だからこそ、ちょっと甘くてもいいから、続けられることを選んでください。
節約とは、「自分の暮らしを整えるための手段」。
あなたが目指すのは“節約生活”ではなく、“気持ちにゆとりのある生活”のはず。
そのために、
- スーパーを変えてみる
- 格安SIMに乗り換えてみる
- そして、自分の体はちゃんとケアする
そんなゆるくてやさしい節約を、今日から少しずつ始めてみませんか?
この記事が、あなたの暮らしとお財布に、ちょっとでもプラスになるきっかけになればうれしいです。