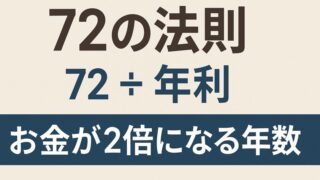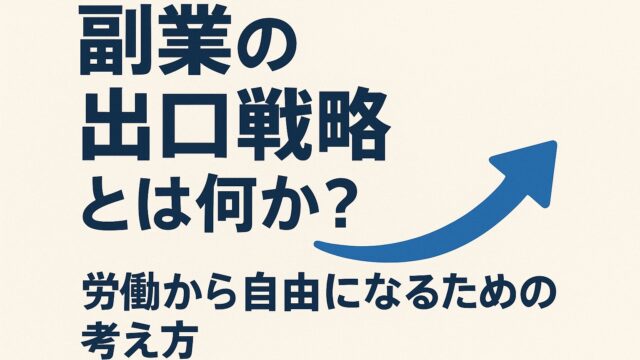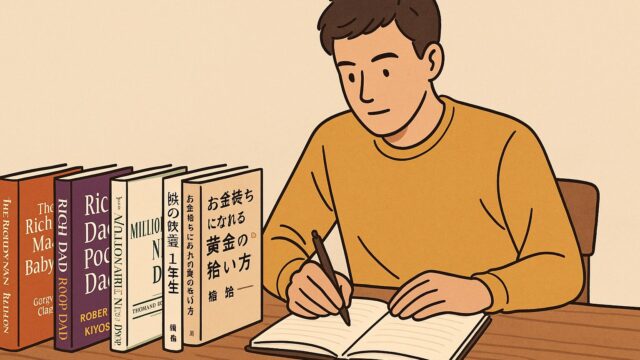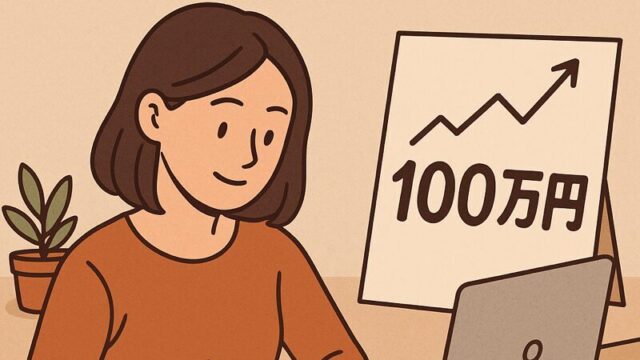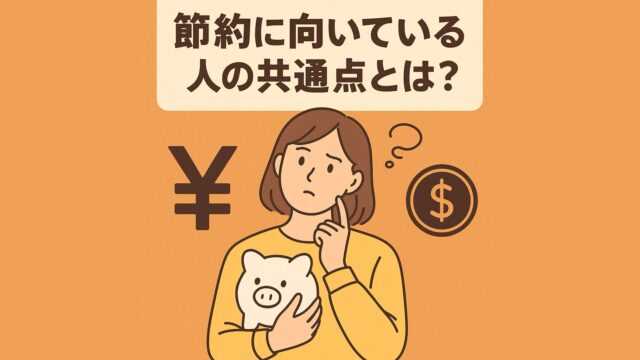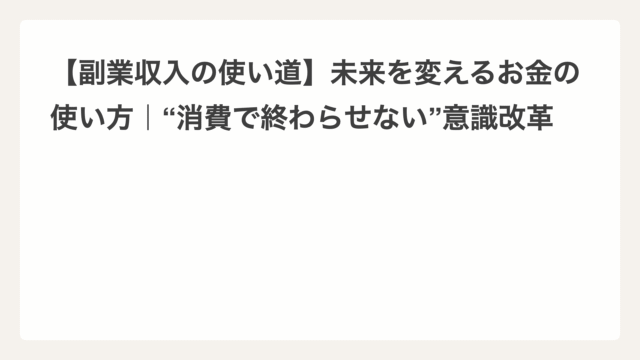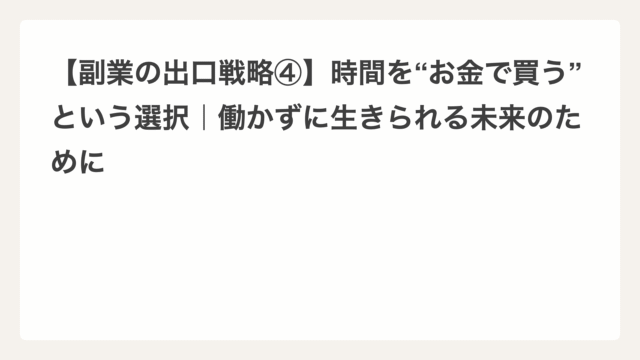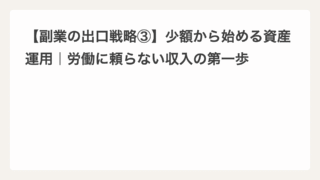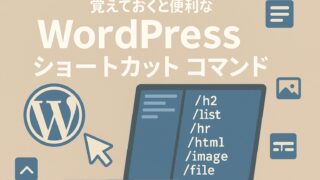「若いうちはリスクを取れ」って、よく聞きませんか?
投資の世界でも例外ではなく、特に話題になりやすいのが「若い人こそレバレッジ投資をするべきだ」という考え方です。
SNSをのぞいてみると、レバナスやブル型ETFで資産を一気に増やした!というような投稿が溢れています。
たしかに、「時間を味方につければレバレッジは合理的」という理屈には納得感もあります。年齢的に回復の時間がある若者なら、確かにチャレンジできるかもしれません。
でも正直なところ、「暴落したらどうしよう…」「自分には耐えられないかも」と不安になる人も多いはず。
全員に当てはまる万能な戦略なんて、存在しません。
この記事では、レバレッジ投資のメリットとリスク、そして「自分に合っているかどうか?」を判断するための軸を、やさしく整理していきます。
なんとなく流されて始めるのではなく、「どう使えばいいのか」を理解したうえで、自分なりのスタンスを見つけていきましょう。
そもそも「レバレッジ投資」とは?
レバレッジって言葉、聞いたことありますか?
もともとは「てこの原理」って意味なんですが、投資の世界ではちょっと違った意味で使われます。
簡単に言うと、自分の持っているお金よりも大きな金額を動かせる仕組みのこと。たとえば「2倍のレバレッジ」がかかるETFなら、株価が1%上がれば2%の利益が、逆に1%下がれば2%の損失が出る、というようなイメージです。
有名なものだと、「レバナス(NASDAQ100の2倍)」とか「日経平均ブル2倍ETF」なんかが知られていますね。
正直なところ、レバレッジ投資の一番の魅力は、少ない元手でも大きなリターンを狙えること。
「一発で資産を増やしたい」という気持ちが強い人には、とても魅力的に映ると思います。
でも一方で、当然リスクも大きくなります。相場が下がったときのダメージも大きいし、上下のブレが大きくなる分、長期保有でパフォーマンスが目減りすることもあるんです。
では、それを踏まえたうえで、なぜ「若い人こそレバレッジを使うべき」と言われるのか。
次の章ではその理由を掘り下げていきましょう。
若い人こそレバレッジが有利とされる理由
「若いうちにこそレバレッジをかけるべき」——そんなふうに言われること、ありませんか?
実はこの考え方、ちゃんとした理由があります。勢いや根拠のない煽りじゃないんです。
まず一つ目の理由は、時間が味方になるから。
若いうちは投資に使える“時間”がとにかく長い。
仮に一時的に損をしても、その後に巻き返すチャンスが何度も訪れます。
20代・30代でスタートすれば、40年、下手すれば50年というスパンで運用できるんです。これは強い。
それに、経験値を積むにはベストな時期でもあります。
たとえ失敗しても、金額が小さいうちならリカバリーしやすい。むしろ、早いうちに「自分はどういうときに不安になるか」とか「どれくらいのリスクに耐えられるか」を体感できるのは大きな財産です。
さらに、元手が少なくてもレバレッジを使えば複利のスピードを加速できる。
資本が少ない若い世代にとって、これは一つの戦略になります。
もちろん、無理にリスクを取る必要なんてありません。
でも、若さには「時間的余裕」と「学ぶ機会」がある。
それを活かす選択肢として、レバレッジ投資は検討に値する手段だと思います。
レバレッジ投資のリアルなリスク
レバレッジ投資って、うまく使えば本当にリターンが大きくなる魅力的な手法です。
でも当然のことながら、いい面だけを見て飛びつくのは危険です。
ここでは、実際に起こりうるリスクを冷静に見ていきましょう。
まず押さえておきたいのが、「下落時のダメージが大きくなる」という点。
たとえば、指数が−5%下がったときに、2倍のレバレッジをかけていたら損失は−10%。
普通に投資していれば「ちょっと下がったな」程度でも、レバレッジだと体感的に倍の衝撃がきます。
特に暴落局面では、資産が一気に減ってしまうスピードに驚くはずです。
「これ、想像以上にキツいぞ…」と感じるのは、レバレッジ投資あるあるかもしれません。
そしてもうひとつ大事なのが「逓減(ていげん)リスク」。
これ、聞き慣れない言葉かもしれませんが、簡単に言うと、価格が上がったり下がったりを繰り返すうちに、最終的な成績が理論値より下がってしまう現象です。
つまり「長く持てば増える」わけじゃない、ってことですね。
さらに、無視できないのがメンタル面のストレス。
含み損を抱えても冷静でいられるか?
そこで売ってしまえば、本来得られるはずだった利益を逃してしまうかもしれません。
次の章では、こうしたリスクとメリットを踏まえて、レバレッジ投資が向いている人/向いていない人の違いを整理していきます。
レバレッジ投資に「向いてる人」「向いてない人」
正直なところ、レバレッジ投資が合うかどうかは、性格や資産状況、そして相場との付き合い方によって大きく変わります。
ここでは、向いているタイプ・向いていないタイプをざっくり整理してみましょう。
向いている人
まず、レバレッジが向いているのは「資金が少ないけれど、積極的に増やしたい人」。
若い世代など、まだ投資元本が小さい人でも、レバレッジを活用することで複利の加速度を高めることができます。
ただし、“資金が少ない”からといって、生活費や必要資金を突っ込むのは絶対にNG。あくまで「失っても生活に影響しない余剰資金」でやることが大前提です。
それから、日々の値動きに一喜一憂せず、冷静に判断できるメンタルを持っている人も向いています。
相場を定期的にチェックできる、つまり「放置せず、ある程度見守れる人」であれば、リスク管理もしやすくなります。
向いていない人
一方で、すでに潤沢な資産を持っていて、わざわざリスクを取る必要がない人は、無理にレバレッジをかける必要はありません。
たとえば、資産の大部分をレバレッジETFに全ツッパ…なんてことをすると、暴落時に一撃で数千万円単位の損失になることも。
また、含み損に弱い人や、相場をまったく見たくない人にもレバレッジ商品は不向きです。
こうした商品は“放置型投資”とは真逆。ある程度の「向き合う覚悟」が必要です。
結局のところ、ポイントは「やるべきかどうか」ではなく、「耐えられるかどうか」。
自分の性格と余力を冷静に見極めて判断することが、後悔しない選択につながります。
セルフチェックのサイトなどで、一度自己診断してみることもおすすめします。
外部リンク: あなたのリスク許容度診断テスト (全国銀行協会)
判断基準とリスクの取り方の工夫
レバレッジ投資、気になるけど踏み切れない——そんな人も多いと思います。
正直なところ、やるかどうかを決める前にまず考えてほしいのが、「自分はどれくらいのリスクに耐えられるか?」ということ。
SNSでの成功談や「これ買えば爆益!」みたいな情報だけで動いてしまうと、思わぬ痛手を負うことも。
だからこそ、まずは自分の性格や資金状況、投資の目的を見つめ直してみましょう。
個人的におすすめしたいのが、「レバレッジ資産はポートフォリオの10〜20%まで」に抑える戦略です。
たとえば、8割は積立NISAやインデックス投資で安定運用し、残り2割でレバレッジ型ETFを取り入れる。
これだけでも、リスクを抑えつつ“伸びしろ”を確保できます。
また、月1回の相場チェックや、定期的なリバランスをする習慣がある人なら、暴落にも落ち着いて対応できる力がついてきます。
大事なのは、「一発逆転」を狙うギャンブルじゃなくて、戦略的にポジションを持つこと。
レバレッジは、扱い方次第で頼れる武器にもなるし、自滅のトリガーにもなります。
自分なりのルールをもって、無理なく投資を続けられる形を選びましょう。
若さを武器にするか、守りに使うか
レバレッジ投資は、若い人にとってとても魅力的な選択肢になり得ます。
長く運用できる時間、少額から始められる柔軟性、そしてたとえ失敗しても立て直す余裕——これらはすべて、「若さ」という資産です。
でも、だからといって全員が「攻めなきゃダメ!」というわけではありません。
正直なところ、精神的に不安定になりやすい人や、リスクへの耐性が弱い人が無理して取り組めば、むしろ損を広げてしまう可能性もあります。
若さには「リスクを取る自由」がありますが、それと同時に「リスクを取らない自由」だってあるんです。
守りを固めることを選ぶのも、立派な戦略。
大事なのは、「自分は何を目指しているのか?」という問いに素直に向き合うこと。
そのうえで、「レバレッジという手段が自分に合っているのか?」を考えていけばいいんです。
若さは、攻めの材料にもなれば、守りの武器にもなる。
だからこそ、焦らず、比べず、自分なりの判断軸を持って、これからの資産形成と向き合っていきましょう。
※ 補足 ※
この記事では、主に「レバレッジ型ETF」などの元本以上の損失が出ない商品を想定して解説しています。
一方で、信用取引やFXなど、証拠金を使ってレバレッジをかける手法では、損失が投資元本を超えてマイナスになるリスクがあります。
特に初心者の場合、仕組みや強制ロスカットの条件を十分に理解していないと、想定外の負債を背負う可能性があるためおすすめできません。
レバレッジの手法を選ぶ際は、「最大損失がどこまでなのか」「追証が発生するかどうか」を必ず確認しておきましょう。