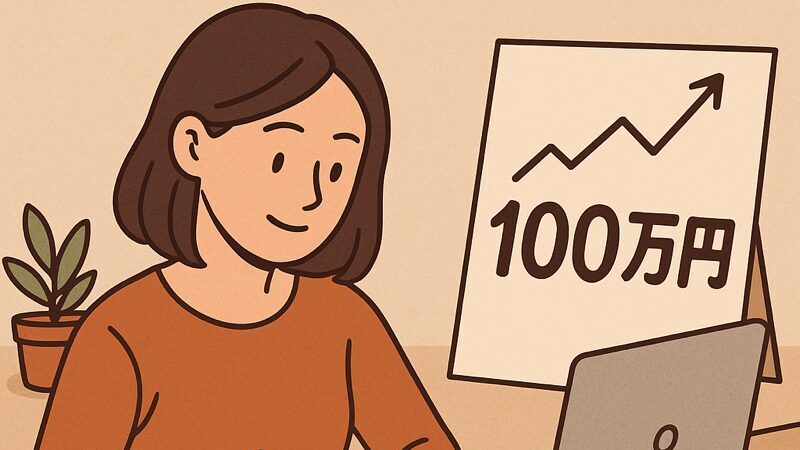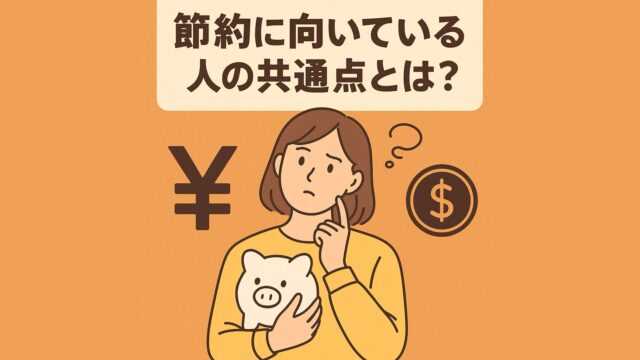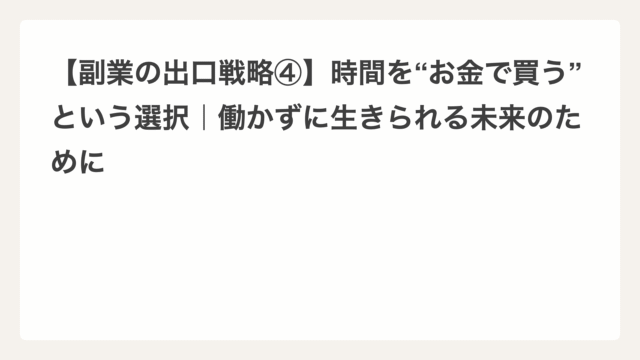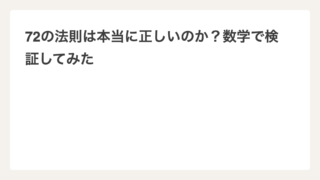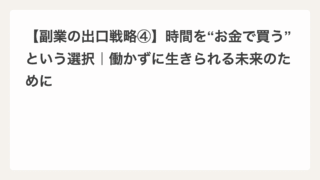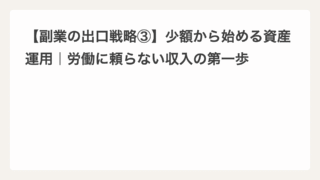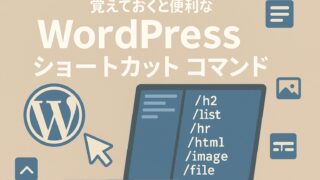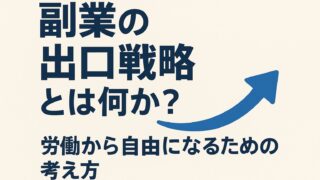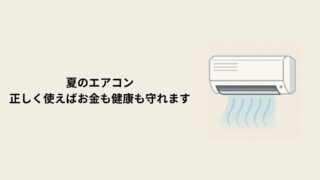社会人になって「まずは貯金100万円を目指しましょう」と言われたことはありませんか?
私の職場でも、入社1年目の研修でそんな話を聞きました。
でも、ただ「貯金100万円を目指そう」と言われても、正直ピンとこない人も多いのではないでしょうか。
そもそも、なぜ“100万円”が目標にされやすいのか?
そして、どんな行動をすれば現実的に到達できるのか?
この記事では、そうした疑問に答えつつ、貯金ゼロから100万円を貯めるためのステップを分かりやすくご紹介します。
特に、まだ社会人になったばかりの方や、貯金が苦手だと感じている方にとって、今日から実践できる具体策をまとめましたので、ぜひ最後まで読んでみてください。
貯金100万円を目指す意義
社会人になってすぐ、月収100万円を超えるような人はごく一部です。
仮にそれだけ稼いでいたら、1ヶ月で貯金100万円も夢ではないでしょう。
でも、現実はそう甘くありません。
たとえば、20代の平均手取りはおよそ20〜25万円。
そのすべてを貯金に回せたとしても、4〜5ヶ月はかかります(実家暮らし+生活費ゼロ前提)。
実際には、家賃・食費・交際費などでお金は出ていくもの。
手取り20万円から毎月5万円を貯金していったとしても、100万円に到達するまでに約20ヶ月(=1年8ヶ月)は必要です。
つまり、100万円とは…
- 「コツコツ継続する力」が試される目標
- 「支出を管理する力」を身につける訓練の場
- 将来の転職・引越し・スキル投資に使える“行動の原資”
この100万円は、単なる貯金額ではなく、「お金と向き合って得られる自己管理スキル」や、
「人生の選択肢を広げる自由度」を与えてくれる、大きな意味を持った金額です。
貯金100万円に至るまでの具体的なステップ
Step①|まずは現状の収支を“見える化”する
「家計簿なんて面倒だし、毎月赤字じゃないから大丈夫でしょ」
そう思っている方ほど、実は“どこにお金が消えているのか”を把握できていないことが多いです。
貯金の第一歩は、収支の現状を知ること。
- 何にどれだけ使っているのか?
- 減らせそうな“ムダ遣い”はあるか?
- 無意識のサブスク課金や外食頻度が高すぎないか?
こうした見直しには、やはり家計簿が有効です。
家計簿アプリを活用しよう
ノートにレシートを貼って…なんて方法では続きません。
おすすめはスマホアプリ。
- レシート撮影で自動入力
- クレジットカードや電子マネーと連携
- 月ごとの支出傾向がグラフで一目瞭然
家計簿アプリを使えば、「無理なく、でも確実に支出を把握する」ことができます。
Step②|100万円までの“距離”を把握する
現状の支出が見えてきたら、次はシミュレーションです。
「あといくら貯める?」「毎月いくらなら、いつ達成できる?」
こうした“ゴールまでの道のり”を可視化することで、モチベーションを保ちやすくなります。
手残り額別|100万円達成までの目安期間
| 月の手残り額 | 100万円達成までの期間 |
|---|---|
| 1万円/月 | 約100ヶ月(8年4ヶ月) |
| 3万円/月 | 約33ヶ月(2年9ヶ月) |
| 5万円/月 | 20ヶ月(1年8ヶ月) |
あくまで一例ですが、月の手のこり額と100万円達成までの目安期間になります。
また、これとは別にボーナスなどの、まとまった額を一気に貯金に回せば、目標達成がグッと近づきます。
(…ボーナス、うらやましいですね)
なぜシミュレーションが大事なのか?
- 成果が見えないと、途中で挫折しやすい
- 数字が見えると、「毎月あと1万円頑張ろう」という具体的行動に変わる
感覚でお金を扱っているうちは、気づいたときには“いつの間にか使っていた”が起きがち。
だからこそ、「計画性のある貯金設計」が必要なんです。
Step ③|固定費の見直しで「手残り額」を増やす
貯金を始めるとき、真っ先にやるべきことが「固定費の見直し」を行い「手残り額」を増やすことです。
なぜなら、固定費は一度見直してしまえば毎月自動的にお金が浮く仕組みになるからです。
仮に、現在の手残り額が1万円の人も固定費を見直すだけで、手残り額が2〜3万円までアップする可能性があります。
固定費ってどんなもの
- 家賃(すぐには変えにくいが、引っ越し時の検討ポイント)
- 通信費(スマホ、Wi-Fiなど)
- 保険(医療保険・生命保険など)
- サブスクリプション(Netflix、Spotify、ジムなど)
「毎月必ず支払っているお金」で、かつ「一度契約すると見直さない」ものが対象です。
例えば、下記のように見直してみると、意外と年間の節約額が増えます。
| 項目 | Before | After | 年間の節約額 |
|---|---|---|---|
| スマホプラン (大手キャリア) | ¥5,000/月 | ¥2,000/月 (格安SIM) | 約36,000円 |
| 医療保険 | ¥10,000/月 | ¥0(国保+貯金で備える) | 約120,000円 |
| サブスク | ¥3,000/月(3件) | ¥1,000/月(1件) | 約24,000円 |
合計で年間18万円以上の固定費が削減可能になります。
この浮いたお金をそのまま貯金口座に自動で移す設定をしておけば、ほぼ意識しなくても貯まっていく構造が完成します。
変動費もちょっとしたコツで節約を
平日の昼ごはんを見直すだけでも、かなりの節約になります。
- コンビニ弁当や外食:¥600〜800/日 → 月12,000〜16,000円
- 自炊 or スーパーの冷凍弁当:¥300〜400/日 → 月6,000〜8,000円
差額は月6,000円以上、年間で7万円超になることも。
忙しい日でも、前日の夕飯を少し多めに作って持参すれば、手間も最小限でOKです。
Step④:ポイント活用で同じ買い物を“割引”で購入する
変動費の節約と聞くと、「我慢すること」「買わないこと」をイメージするかもしれません。
でも、実は「同じものを、少しだけ賢く買う」だけでも立派な節約になります。
その鍵を握るのが、ポイント還元の仕組みです。
たとえば、楽天市場での買い物。
何も考えずに普通に買うと、ポイントは1%しか付きません。
でも、工夫次第で2%〜10%以上の還元を狙うことも可能です。
例えば、月3万円の買い物を3%還元で購入した場合
→ 年間で10,800円分
これが5%なら18,000円分、10%なら36,000円分。
つまり、何もしていない人との差が1年で数万円になるということです。
具体例:私が実践している“ポイント三段活用”
私がよく使っているのは、以下のような三段活用テクニックです。
ケース①:楽天市場での日用品・書籍など
- ハピタス経由で楽天市場にアクセス(1%)
- 楽天カードで決済(+1%〜3%)
- SPU(楽天ポイントプログラム)で条件を満たす(+α%)
→ 合計で 4〜8%還元になることもあります。
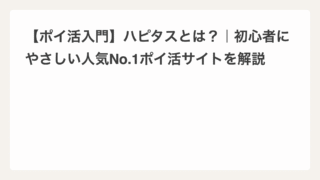
ケース②:マツモトキヨシで日用品を買う場合
- ハピタスを経由してマツモトキヨシの公式通販へ(1%〜)
- 楽天カードで決済(+1%)
- マツキヨポイント&楽天ポイントが両方つくケースもあり
→ トータルで 3〜5%の“見えない割引” に。
ケース③:コスメの通販
- 楽天Rebates(リーベイツ)を経由(4%〜の高還元あり)
- 楽天カード決済
- キャンペーン時はさらに+2〜5%
→ タイミングが合えば 1回の買い物で10%超還元 も可能です。

100万円を貯めると何が変わるのか?
① 20代の平均を超える“金額的自信”が手に入る
金融広報中央委員会が2023年に発表した調査によると、
20代単身世帯の貯蓄の中央値は30万円、さらに約36%の人が貯蓄ゼロという実態が明らかになっています。
このデータから見ると、100万円の貯蓄がある20代は、すでに全体の上位30%に入る水準に達していると考えられます。
これは単なる数字の話ではなく、
「お金を貯める習慣がある」「計画的に支出管理ができている」という、金融リテラシーの高さを示すひとつの証明にもなります。
また、統計的な分布モデルに当てはめると、100万円の貯蓄は“貯金偏差値60以上”に相当すると考えられ、自分にとっての大きな自信と客観的な成果の指標にもなり得るでしょう。
② 将来の選択肢が広がる
100万円の貯蓄があることで、人生のさまざまな場面で“選べる余裕”が生まれます。
たとえば、転職や独立といったキャリアチェンジ。
新たな道に進む際には、一時的に収入が減ることもありますが、貯蓄があれば焦らず自分に合った選択ができます。
また、引っ越しや家具の買い替えなど、ライフスタイルを変えるタイミングでも、金銭的な不安に左右されずに行動できるのも大きなメリットです。
さらに、100万円あれば、スキルアップや副業への投資資金として活用することも可能です。
プログラミングスクールや資格講座など、将来の収入につながる自己投資の選択肢がぐっと広がります。
まとめ|100万円はゴールではなく“スタートライン”
100万円を貯めるという経験は、単に貯金額が増えるだけではありません。
それ以上に大きいのは、「貯める力」という一生使えるスキルが身につくことです。
特に、固定費の見直しや日々の支出管理を通じて、お金の流れを自分の手でコントロールできる感覚を得られるのは大きな財産です。
そして、100万円が貯まったその先には、「増やすステップ」への移行が待っています。
副業に挑戦する、積立NISAや投資信託を始めるなど、未来の選択肢を広げるための資金として使えるのがこの金額の真の価値です。
このように、100万円は決して終点ではなく、自由な生き方・働き方を実現するためのスタートライン。
ここから、あなた自身の資産形成の道を切り拓いていきましょう。