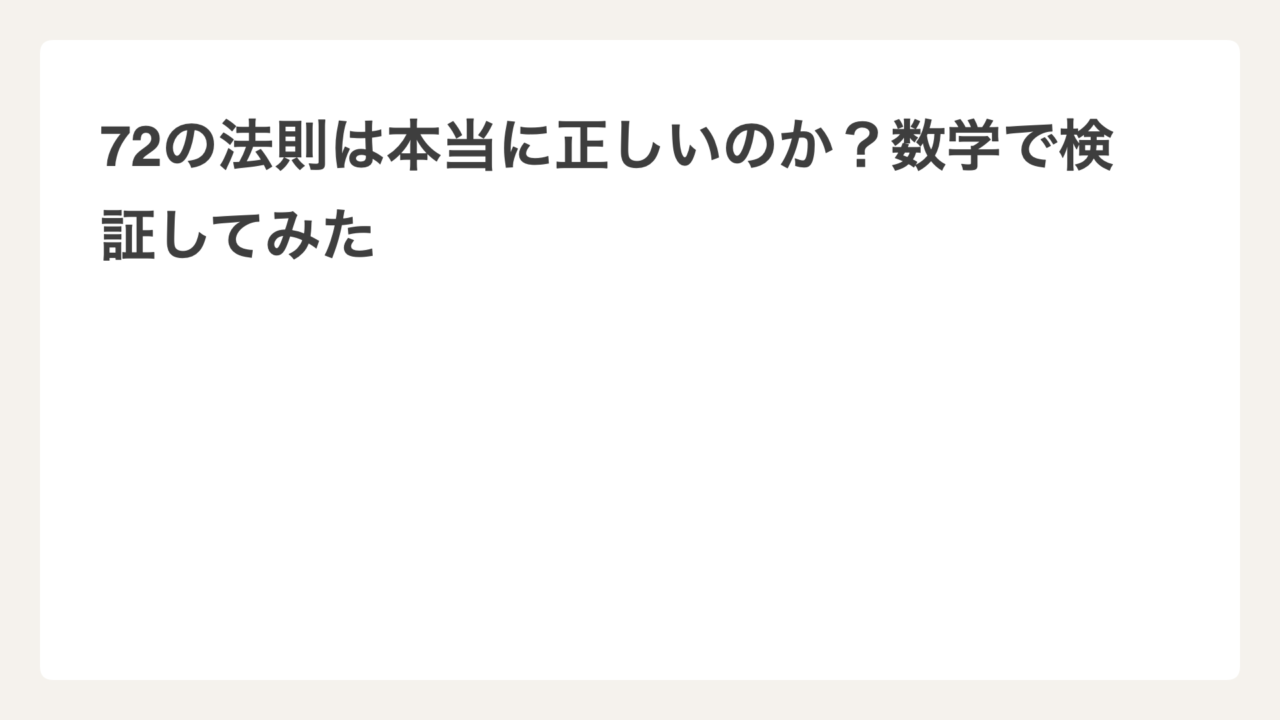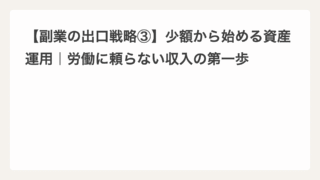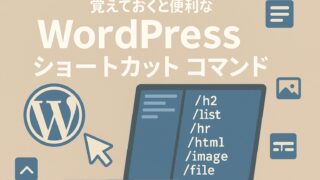「72の法則」って、一度は聞いたことがある人が多いのではないでしょうか?
たとえば、「年利6%で運用すれば、72 ÷ 6 = 12年でお金が2倍になるよ」といった形で紹介されることが多いこの法則。とてもシンプルで覚えやすいので、投資初心者向けの本や動画でもよく登場します。
でも、ふと思ったことはありませんか?
「なんで“72”なんだろう?」
「他の数字じゃダメなの?」
「そもそもこれって、ちゃんと正確なの?」
実はこの72の法則、数学的には少しズレているとも言われており、代わりに「69の法則」の方が正確だとする説もあるのです。
本記事では、この「72の法則」と「69の法則」を比べながら、
- なぜ“72”が使われているのか?
- “69”の方が正確ってどういうこと?
- 実際、どっちを使えばいいのか?
といった疑問を、やさしく・実用的に解き明かしていきます。
数字に強くなくても大丈夫。
ちょっとした“感覚のものさし”として使えるようになることが、この読み物のゴールです。
72の法則とは?|超ざっくりお金が2倍になる法則
まずは、本題の中心となる「72の法則」について、改めて整理してみましょう。
これはものすごく簡単な法則です。
72 ÷ 年利(%) = お金が2倍になるまでの年数
たとえば、年利6%で資産運用している場合は:
72 ÷ 6 = 12年
つまり、「12年で資産が2倍になる」というわけです。
これ、めちゃくちゃ便利じゃないですか?
なぜこの法則が人気なのか?
正直なところ、この法則が投資初心者の間で人気なのには理由があります。
以下のような特徴があるからです:
暗算できるほどシンプル
ほとんどの人が電卓なしで計算できるレベルの式です。
「年利が9%なら、72 ÷ 9 = 8年」……このくらいなら、頭の中ですぐ出ますよね。
感覚でつかめる
「この利回りなら何年で2倍かかるか」がサッとわかるだけで、“時間とお金の感覚”が自然と身につくようになります。
たとえば、年利2%では「36年」、年利12%では「6年」。
「金利ってたった数%の違いでも、時間的にはこんなに差が出るんだ」と、数字の重みが実感できるようになります。
投資だけでなく、詐欺を見抜く感覚にも
実はこの法則、「本当に投資商品なのか、それとも怪しい案件なのか?」を見抜くファーストフィルターとしても使えます。
たとえば、「1年で資産が2倍になります!」と謳っている投資案件があったとしましょう。
それって、72 ÷ 1 = 72%の年利ってことですよね?
(「年利72%じゃ、1年で2倍にならないじゃん」というツッコミは置いておき)
年利72%なんて、常識的にはあり得ません。
なので、この法則を知っているだけで「ちょっと怪しいかも?」という感覚が自然と身についてきます。
つまり、「72の法則」は“感覚のものさし”
もちろん、あとで述べるようにこの72という数字は完全に正確なわけではありません。
でも、このシンプルな式から得られる「時間とお金の感覚」は、数字以上に大切なものです。
計算ツールでも、アプリでもなく、自分の頭でざっくり判断できる力。
それこそが、「72の法則」がこれほどまでに長く愛されている理由なのだと思います。
実は“69”が正しかった?数学的に見た本当の法則
「72の法則って便利だけど、本当に“正確”なの?」
そう思った方、実はかなり鋭いです。
というのも、72という数字は実用的には優れているものの、数学的には厳密な値ではないんです。
実際、より正確な数字としてよく挙げられるのが「69」。
ではなぜ「69の法則」が生まれたのか、どこから導き出されたのかを、少し数学の力を借りながらやさしく見ていきましょう。
(詳しくはこちらの記事でも書いています)
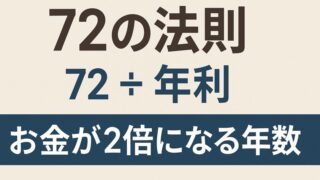
お金が2倍になる時間を“ちゃんと”計算してみる
まずは、複利の増え方を表す式からスタートします。
(1 + r)n = 2
ここで、
- r は年利(例:5%なら0.05)
- n は資産が2倍になるまでの年数
この式の意味は、「毎年 r の利回りで増え続けたら、n 年後に資産が2倍になるよ」というものです。
この「n」を求めたい場合、式の両辺に対数(log)を取ります。
log( (1 + r)n ) = log(2)
→ n × log(1 + r) = log(2)
→ n = log(2) ÷ log(1 + r)
ここで注目すべきは、「log(2)」の値。
これは定数で、約0.6931。
つまり、
n = 0.6931 ÷ log(1 + r)
さてここで、年利が小さい場合(例えば3%〜10%)には、log(1 + r) を r で近似することができます。
これは高校数学のテイラー展開という手法による近似で、
log(1 + r) ≒ r(ただし r が小さい場合)
が成り立ちます。
この近似を代入すると、
n ≒ 0.6931 ÷ r
ここで、r を「%表記」に変えるために、×100をしておきましょう。
n ≒ 69.31 ÷ 年利(%)
出ました、69の法則です。
つまり、数学的には「69」の方が正しい
結論として、純粋な数式ベースで導いた結果としては、72よりも「69」の方が正確です。
このことから、「69の法則」の方が“正しい”とする数学的立場も根強くあります。
| 年利(%) | 69 ÷ 年利 | 72 ÷ 年利 | 差(年) |
|---|---|---|---|
| 3% | 23.0年 | 24.0年 | +1.0年 |
| 5% | 13.8年 | 14.4年 | +0.6年 |
| 7% | 9.86年 | 10.3年 | +0.44年 |
| 10% | 6.9年 | 7.2年 | +0.3年 |
誤差はあるけれど、極端にズレるわけではありません。
むしろ、ここまで近いなら「実用的には72でも良くない?」という話が次の章につながっていくのです。
それでも72が使われる理由とは?
前章で見たとおり、「69の法則」の方が数学的にはより正確です。
ではなぜ、私たちがよく耳にするのは「72の法則」なのでしょうか?
実はそこには、“実用性”と“教育効果”を優先した理由があるのです。
理由①|72は割り切れる数が多く、暗算に向いている
まず1つ目の理由は、「計算しやすさ」。
72という数字は、以下のように多くの整数で割り切れるという特徴があります。
2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36…
これに対して、69は素数に近く、割り切れる数が非常に限られています。
たとえば、
- 年利6%:72 ÷ 6 = 12年
- 年利8%:72 ÷ 8 = 9年
- 年利9%:72 ÷ 9 = 8年
このように、頭の中でもサッと答えを出せるので、初心者向けの教材や本に最適なのです。
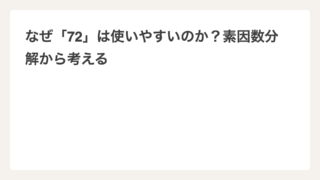
理由②|実務上の誤差が非常に小さい(±0.5年程度)
「でも、ちょっとくらい正確じゃなくて大丈夫なの?」
という声も聞こえてきそうですが、実は誤差は極めて小さいんです。
| 年利(%) | 69 ÷ 年利 | 72 ÷ 年利 | 誤差(年) |
|---|---|---|---|
| 4% | 17.25年 | 18年 | +0.75年 |
| 6% | 11.5年 | 12年 | +0.5年 |
| 8% | 8.625年 | 9年 | +0.375年 |
| 10% | 6.9年 | 7.2年 | +0.3年 |
この表を見ると、年利3%〜10%の範囲での差は0.3〜1年程度。
資産形成はもともと10年単位のスパンで考えることが多いため、誤差としてはほとんど気にならないレベルなのです。
理由③|教育・啓発ツールとして普及した歴史がある
もうひとつ大きな理由は、「72の法則は“教えるツール”として圧倒的に優れている」という点です。
- シンプルな式 → 覚えやすい
- 計算がラク → すぐに使える
- 誤差が小さい → 現実的に使える
- 数字が印象的 → 人に教えたくなる
この「ちょうどよさ」が、金融教育や投資啓発の現場で愛されてきた背景なのです。
書籍・YouTube・セミナーなど、初心者に投資の魅力を伝える場では「正確さよりも感覚に届くこと」が重要。
その意味で、「72」はちょうどよく、“数字のマジック”として機能しているのです。
72の法則が意味する「資産の時間感覚」
ここまでの章で、「72の法則は数学的に完全じゃないけれど、実用性は抜群だよ」という話をしてきました。
でも実は、この法則が本当に価値を発揮するのは、“資産の時間感覚”を育てることにあります。
お金が「どれくらいのスピードで増えるのか」が感覚的にわかる
たとえば、「年利3%で運用している人」と「年利6%で運用している人」。
- 年利3%:72 ÷ 3 = 24年で2倍
- 年利6%:72 ÷ 6 = 12年で2倍
この違い、たった3%の差で、2倍までの時間が半分になるわけです。
このインパクトを、頭で理解するだけでなく「感覚」として身につけられるのが、72の法則のすごいところ。
時間と利回りのバランスが見えるようになる
投資の世界では、「利回りが高い=すごい!」ではありません。
むしろ、自分の資産形成ゴールまでに“どれくらいの時間があるか”を知ることが、戦略の出発点になります。
たとえば:
- 30歳の人が60歳までに資産を2倍にしたい → 必要な年利は 72 ÷ 30 = 2.4%
- 一方、10年で2倍にしたいなら → 年利 7.2% が必要
こうした計算がサッとできるようになると、「この投資商品は自分のライフプランに合ってるのか?」という視点を持てるようになります。
詐欺や過剰なうたい文句を見抜く“基準”になる
実は、72の法則は投資詐欺を回避するためのリテラシーツールとしても使えます。
たとえば、「3年で2倍になりますよ」と言われたら、こう計算してみましょう。
72 ÷ 3年 = 年利24%
…ちょっと、現実的ではないですよね?
S&P500の長期平均でも6〜7%ですから、年利20%超はかなりのハイリスク。
こうした“数字で見る目”があるだけで、怪しい話に引っかかるリスクがグッと減ります。
「感覚のものさし」としての72の法則
個人的には、72の法則は「小学生でも使えるお金のツール」だと思っています。
- 割り算だけでOK
- 年数や利回りの意味が直感でつかめる
- 自分で考える習慣が身につく
こういう「数字と時間を結びつける感覚」は、投資だけでなく、貯金、教育費、老後資金、インフレ…さまざまな場面で活かせます。
つまりこれは、単なる“便利な式”ではなく、未来に向けた思考のトレーニングツールなんです。
まとめ|数字の正確性より、感覚のものさしとして活用しよう
ここまで「72の法則」と「69の法則」を比較しながら、その数学的背景や実用性、そして使い方について掘り下げてきました。
結論として、こう言えると思います。
正確さを求めるなら「69」
感覚で使いたいなら「72」
大事なのは“自分にとって使いやすいかどうか”
数字に強い人や、Excelで緻密に資産設計をしたい人には、69の法則の方がしっくりくるかもしれません。
でも、多くの人にとっては「72÷年利」というシンプルな計算式が、資産と時間を考える“はじめの一歩”になってくれるはずです。
正確性と実用性、どちらが大事?
私たちはつい「正確な数字」や「正しい計算式」に目を向けがちです。
けれど、日常生活や長期の資産形成では、“おおよその目安”がわかることの方が、むしろ大切だったりします。
なぜなら、資産形成の成功は「途中で投げ出さずに続けられるかどうか」が最大のカギだからです。
感覚的にわかりやすく、すぐに使えて、行動の背中を押してくれる——
そんな意味で、「72の法則」はいまも多くの人に選ばれているのです。
他の資産倍増ルールも使ってみよう
今回は「資産が2倍になるまでの年数」を扱いましたが、実は以下のような“ほかの倍増ルール”も存在します。
- 115の法則 → 年利から「資産が10倍」になるまでの年数を出せる
- 144の法則 → 年利から「資産が3倍」になるまでの年数を出せる
こうしたルールもあわせて使うことで、「◯年後にいくら必要だから、年利何%を目指そう」という考え方がより立体的になります。
最後に|数字と“付き合う力”を育てよう
金融リテラシーとは、「難しい数式を覚えること」ではなく、「数字を使って未来を考えられること」だと思います。
72の法則は、その第一歩として、とてもシンプルで、だけど奥深いツールです。
正確さにこだわりすぎず、自分の“感覚のものさし”として、ぜひ使いこなしてみてください。